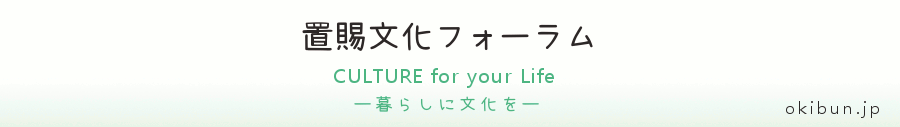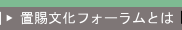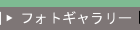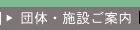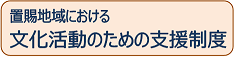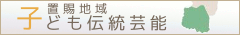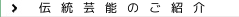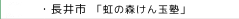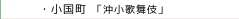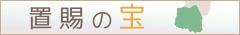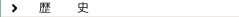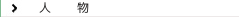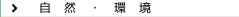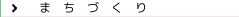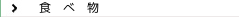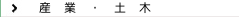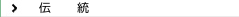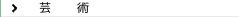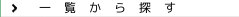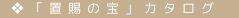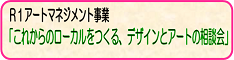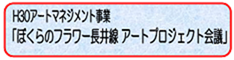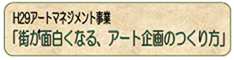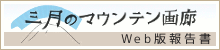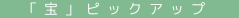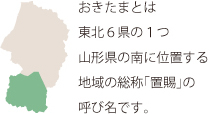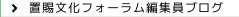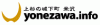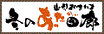上杉家の智将
兼続が生まれた年、織田信長が桶狭間で今川義元を破りました。信長は、それまでの農業的価値観を軸とする社会にかわって新たに商工業経済を軸とする社会を創り出そうとし、幕府や寺社勢力などと戦いました。そうして、義・伝統・宗教の大切さを説き経済に偏重することを善しとしない上杉謙信と対立し、戦国最強の上杉謙信が没すると、上杉家を滅ぼそうと一気に攻勢を強めました。その結果、相続争いで分裂していた上杉家は、本能寺の変が起きなければ滅亡も有り得るところまで弱体化しました。そのとき、相続争いに決着をつけ、上杉家再建の道を開いたのは、直江兼続のはたらきでした。 豊臣秀吉の片腕だった石田三成と親交のあった兼続は、上杉家を豊臣政権の重職につけ秀吉の後ろ盾を得ることに成功。東日本において確かな人材に恵まれていなかった秀吉は、上杉景勝を歓迎し、徳川家康(関東)の背後を押さえ伊達政宗(東北)の出口を封じる位置にある会津(福島県)と米沢を、景勝と兼続にそれぞれ任せることにしたのでした。戦国最強だった上杉家の実力と、決して人を裏切らない義の教えをしっかりと受け継いだ景勝・兼続は、家康と戦うことができ、豊臣家を裏切る心配が無かったからです。
「長谷堂城の戦」図解へ 家康は、関が原の戦に関連して敵対した大名たちのほとんどを潰しましたが、上杉家を潰すことはできませんでした。豊臣家を裏切らない上杉の「義」は、人々に「上杉の敵イコール豊臣家の敵」という方程式を与えていました。「自分が豊臣秀頼の後ろ盾になる」という立場で多くの大名を味方に引き入れた家康にとって、上杉家を潰せば大量の大名たちが離反し、徳川家が滅ぼされてしまうからでした。 その後、上杉家は家康によって120万石から米沢30万石に減封されますが、兼続の奔走によって両者は和解。初代米沢藩主となった上杉景勝は、上杉家存続の礎を築き、謙信の教えを後世に伝えたのでした。 要塞「米沢」
この難題と取り組んだ直江兼続は、全国でも他に例を見ない城下町の建設を行います。 まずは家臣団の食糧確保です。新田を開いても農民が確保できないため、下級家臣団を城外に住まわせ、田畑を開いて自給自足の生活をさせました。彼らのおかげで上杉家は、食糧不足・農民不足を解消し、財政も軽減することができました。南原の荒地を田畑に変えた堀立川・御入水川、西原に田畑を開いた木場川などは、400年経ったいまも田畑に灌漑(かんがい)用水を提供し続けており、長きに渡って人々の生活を支える施設として平成20年度土木学会選奨土木遺産「直江兼続治水利水施設群」に認定されています。また彼らは、山形に通じる最上街道、伊達軍の侵入が懸念される福島街道、徳川政権下に入った会津に通じる会津街道沿いの防衛も任されました。「原方衆(はらかたしゅう)」と呼ばれる彼らは、家康を向こうに回して天下を動かした上杉家の歴史の証なのです。
果たして、これだけの何重もの守りを突破して、本丸にたどり着ける敵がいるものでしょうか。本丸前の上級家臣団屋敷で手間取れば、両側から謙信・信玄の最強軍団に攻め込まれ、その周りから鶴翼の陣形に並んだ旗本衆に包み込まれてしまうのです。そのうえ米沢城には、原方衆がもっとも多く住む南原から城門を閉ざした城内に集結するための、秘密の抜け道まで準備されていました。 いや、それ以前に、米沢盆地に来攻した敵には、八幡原に陣を張ろうとする段階ですでに大きな障害がありました。陣を張るのにもっとも適した地に、前田慶次が居を構えていたのです。まさに米沢は、町自体が難攻不落の巨大要塞だったのです。 現在、直江兼続がつくった米沢城下町は、その95%以上が変わらずに残っています。大正時代に2度の大火に見舞われ城下町は失われたと思っておられる方も多いようですが、大火が無くとも400年前の建物が残ることは無理でしょう。しかし、城下町の命は「区画」(当時は「縄張り」と言いました)です。区画は道路で決まります。その道路の95%以上が、現在もそのまま使われています。新しい道路がたくさん追加されても、当時の道路はそのまま残り、町の姿を現在に伝えています。私たちは現代もまだ、直江兼続がつくった町に生かされ毎日を暮らしているのです。 上杉の「義」、兼続の「義」 上杉の「義」は、上杉謙信に始まります。しかし、そもそも謙信が活躍した戦国時代においては、「義」は戦国武将共通の倫理観でした。 鎌倉時代、武士の歴史が始まって間もない時代には、武士の理想は「血気の勇」でした。彼らにとっては、死の恐怖に打ち勝つ強さと気勢こそが「勇気」ある者の姿でした。乱暴に言えば、血の気の多さが勇気の目安となっていたのです。しかし、鎌倉時代後半から室町時代にかけて、中国から伝わった儒学に触れた武士たちは、血の気の多さから多くの人を斬ることは「強さ」というよりもむしろ「狂気」であり、本当の「強さ」は「正義」「仁義」のために自らを制することと考えるに至ります。つまり「義を見てせざるは勇無きなり」なのであり、戦うことも戦わないことも、「義」に従って行動できることが本当の「勇」であると考えるようになったのです。
上杉景勝、直江兼続は、この謙信の「義」を受け継ぎました。しかしその内容は、彼らの立場の変化にともなって変化していきました。 越後にいたころの上杉家家臣団は、各々が各地に点在する山城を拠点とし、私的に領地を所有していました。彼らは経済的・軍事的に自立しており、その時々の利害関係によって敵味方になって争ってもいました。したがって、このころの景勝の立場は、自立した家臣たちの「統率者・指導者」であると言えます。そして、その立場を全うするためには、それにふさわしい人間であることを認めてもらうことが必要でした。そのために景勝は、上杉謙信の後継者であることをアピールし、謙信の威光を掲げてカリスマ性を示しました。この当時の上杉の「義」は、「統率者・指導者」としての人格を示すための、きわめて個人的で観念的な「人間としての生き方」だったのです。 しかし、豊臣秀吉によって上杉家が会津に移されたことで、家臣たちは自分の城や領地を失いました。そして彼らは、景勝が秀吉から与えられた所領(領地)の中から、新たに所領を分けてもらうことになります。このとき景勝の立場は、家臣団全体の財産を所有する「領主」へと変わり、家臣団の安全と生活を保障する責務を負うことになりました。それとともに上杉の「義」も、それまでの個人的な「人間としての生き方」から、家臣団やその家族に対する「責務」に変わりました。言い換えれば、仲間同士のリーダーの「義」から、組織の経営者の「義」へと進化したのです。
こうして3つの立場の「義」を身につけた上杉家は、豊臣秀吉の没後に次のような動きをします。 秀吉が没し、天下取りに動き出した徳川家康は、先ほど述べたように、自分があたかも豊臣秀頼の後ろ盾のような態度を示し、多くの大名たちを騙しました。つまり、不「義」なやり方で政権を奪おうとしたのです。これに騙されなかった上杉景勝・直江兼続は、「人間としての生き方」である「義」の立場から、家康と対決しました。 しかし、家康が関が原の戦に勝利し、天下が家康のものになることが確実になると、景勝・兼続は家臣団の生活を保障する組織経営者の「義」の立場から、生き残るために家康の傘下に降りました。そして、家康が私利私欲に陥らずに善政を行おうとする姿勢を見せると、上杉家は天下国家全体の安寧を守る「大義」の立場から、徳川政権の確立に協力しました。 謙信の時代、人々から高く評価された上杉の「義」は、景勝・兼続の成長とともに進化し、新しい時代を迎えても、天下にその素晴らしさを認められたのでした。 学問の人 戦国武将の中には、学問に熱心だった者が少なくありませんでした。軍法・兵法は当然のこと、健康保持のための医学や、必勝を期しての占いまで、勝ち抜くため、生き残るために学問は不可欠だったのです。しかし、やはりそのレベルには個人差が大きく、兵法では「風林火山」の武田信玄、医学では長生きして大願を成就した徳川家康などが知られています。もちろん直江兼続も多方面にわたる学問を修めており、自ら著した『軍法』、息子のために手に入れた薬の処方を詳細に書いた手紙などが遺されています。 しかし、江戸時代の初めに活躍した新進気鋭の儒学者 藤原惺窩(ふじわらせいか)は、知人への手紙で、武将の中で学問をよくする者は5人だと記しています。その筆頭が上杉謙信であり、5人の中に直江兼続が入っています。上杉家は、君臣ともに学問に優れた家だったと言うことができるでしょう。(他に高坂昌信、小早川隆景、赤松広道) では、なぜ上杉家なのか。当時、学問を修める場といえば寺院でした。とくに武家の間では、鎌倉時代以降に中国文化の窓口となった臨済宗(禅宗)を通じて「五山文学」を中心とする漢学が導入され、禅宗寺院で教導されていました。伊達政宗も幼少時に臨済宗の資福寺で学んでいますし、直江兼続が上杉景勝と共に曹洞宗(禅宗)の雲洞庵で学んだことは大河ドラマでも描かれました。しかし、多くの武将は幼少期のみで、その後は寺院から離れてしまいます。これに対して上杉謙信は、生涯を禅僧(曹洞宗)として生きた人です。それだけでも、藤原惺窩が謙信の名を筆頭に挙げたことが頷けます。また、五山文学は漢詩文を得意としますが、謙信も兼続も漢詩の秀作を遺しており、そのレベルの高さがうかがえます。 室町時代の日本文学を代表するものに、連歌があります。複数人で歌を詠み次ぐ連歌は、コミュニケーションの道具としても有効で、公家・武家から庶民にまで広まりました。これを全国に伝え、連歌全盛の礎を築いたのが、飯尾宗祇(いいお/いのお そうぎ)という人物です。中でも宗祇は越後国上杉家には最多の7度も足を運び、連歌を指導しました。そのためか、上杉家は全国でもとくに漢詩文・連歌のレベルが高く、1602年に亀岡文殊(高畠町)で詠まれた漢和連句(連歌に漢詩を混ぜたもの)の作品は、その水準の高さと詠み手の多さにおいて他に類を見ないと研究者も驚いています。
兼続は、自らも学問書を出版しています。中国古典研究家の必読書といわれる詩文集『文選(もんぜん)』を、当時最新の銅活字印刷で私費出版し、日本の学問界に貢献しました。後に、江戸幕府の儒学者林羅山が上杉景勝に『文選』を求めて入手しており、現在に伝えられています。この出版が1607年だったことにも驚かされます。その前年に上杉家は、江戸城の桜田門石垣工事を命じられ、翌年から米沢城下町の建設が始まるからです。そのような多忙な時期に学問書を出版する熱意とは、どれほどのものだったのでしょうか。研究者の間では、この時期に相次いで没した2人の娘を追悼するための詩文集だったという見方もありますが、それもまた兼続らしいやり方だったと言えましょう。 この『文選』は、もともとは中国の南北朝時代に文化政策に力を入れた梁の国でつくられたものです。この他にも兼続は、梁においてつくられた『千字文』も修めていました。その中に含まれる言葉が「龍師火帝(りょうしかてい)」です。この言葉が刻まれた巨大な石が現在、堀立川(兼続が開削した灌漑用水路)の取水口「猿尾堰(さるおぜき)」に置かれています。「龍師」は水神、「火帝」は太陽の神すなわち農業神であり、南原から塩井地区までの田畑を潤す堀立川にふさわしいとされています。しかし江戸時代の記録の中に、この石にまつわる出来事が登場します。 記録の中でこの石は「直江石」と呼ばれています。そして記録には、「直江石」は2つあったと書かれています。上杉鷹山の時代、松川の中に巨大な石がありました。そこで竹俣当綱が、目障りだから片付けるようにと命じて石を転がそうとしたところ、石の下面に「直江山城守」の文字が刻んであるのが見つかりました。これが1つ目の「直江石」です。作業に当たった家臣たちは、「あの直江兼続のことだから、必ずや何らかの目的があって置いた石に違いない。動かさない方が良いのではないか。」と進言しましたが、そのまま石は片付けられました。ところがその石は、大雨で発生する鉄砲水をぶつけて水勢を弱める役目を果たしていたのです。やがて大雨が降り、鉄砲水はまっすぐに堤防に襲い掛かり、この石とセットで築造された直江石堤が決壊してしまいます。上杉鷹山はその修築工事に当たりますが、そのときに、決壊した石堤の奥からひときわ大きな石が現れ、その表面に「龍師火帝」と刻まれているのが確認されました。水神の力で洪水から田畑を守り、農業神の力で豊作を祈ったものでした。そこで、「龍師火帝」の石は堤から取り出されて見える所に掲げられ、石堤が修築されたということです。
「卓錫神祠霊地隣 講筵平日絶囂塵 禅林寺裏枝々雪 認作洛西華園春」 (読み下し:卓錫す神祠霊地の隣に 講筵平日囂塵を絶す 禅林寺裏 枝々の雪 認めて洛西華園の春と作(な)す) (意味:和尚は神祠霊地の隣のこの場所に杖を留められた。講義はすでに毎日行われていて、かまびすしい俗塵から絶たれた別天地をなす。禅林寺境内の枝々の雪の美しさ。この素晴らしい眺めを、あの洛西花園の妙心寺の春景色に見立てたい。) 石田三成との友情 直江兼続は、石田三成と同い年です。知的で武にも優れた能力、最後まで豊臣家を裏切らなかった人柄など、両者は互いを認め通じ合うところがあったものと思われます。人間関係には多少不器用だったと思われる石田三成も、兼続とは良い関係を築いていたことでしょう。
関が原の戦で三成が亡くなると、三成の子(おそらく三男)が兼続を頼って米沢にやって来ました。上杉家は、まだ城下町も出来ておらず、徳川家との関係も最悪の状態にあったため、兼続は彼を堀金村(川西町)に隠します。そして兼続は、城下町建設に際して彼のために商家を準備してやりました。幕府の目を忍んで素性を明かせない彼を武士に取り立てる訳にもいかず、城下において自立させるためには最適の方法だったと言えましょう。その商家の場所は、最上義光が米沢城下に侵攻した場合にまっ先にぶつかる場所、同時に兼続の妹を妻とし直江家の庇護(ひご)を受けた色部氏の屋敷が後ろ盾となる場所(現米沢市中央4丁目10-41)でした。当家は代々「堀金」姓を名乗り、幕末まで続きましたが、その後に途絶えたということです。また、分家は「石田」姓を名乗って東町に商家を構えました。 法泉寺(もと禅林寺)の文殊堂(第2代絶山和尚が創立)の前には、直江兼続が建てた石田三成供養碑と伝えられる石板があります。江戸幕府に知られてはいけないと文字記録には残さず、代々住職の口伝によって言い伝えられてきました。二人の友情は形となって、400年余の間、米沢の地に伝えられているのです。 直江兼続関連 略年表へ  〇掲載日 平成24年6月 〇執筆者 遠藤 英(九里学園高等学校 教員) 主な著書 「直江兼続の素顔」 「直江兼続物語 米沢二十年の軌跡」(新潟日報事業社) 「直江兼続がつくったまち米沢を歩く」 「米沢学事始 上杉鷹山の訓え 明るい未来を拓くために・・・」 〇編集 勝見弘一(置賜文化フォーラム) 〇写真提供・関連施設 上杉神社稽照殿 最上義光歴史館 財団法人 宮坂考古館 米沢観光物産協会 福島県立博物館 〇関連「宝」記事 前田慶次 〇関連ページ 置賜探検隊 印刷用PDFはこちら |
(C) 置賜文化フォーラム All Rights Reserved.